こんにちは。プロフィール株式会社の浅見です。
こちらのルームでは、住宅業界の皆様にとって有益なLINE活用の方法やデジタルマーケティングのポイントやコツについて、お伝えしていきます。
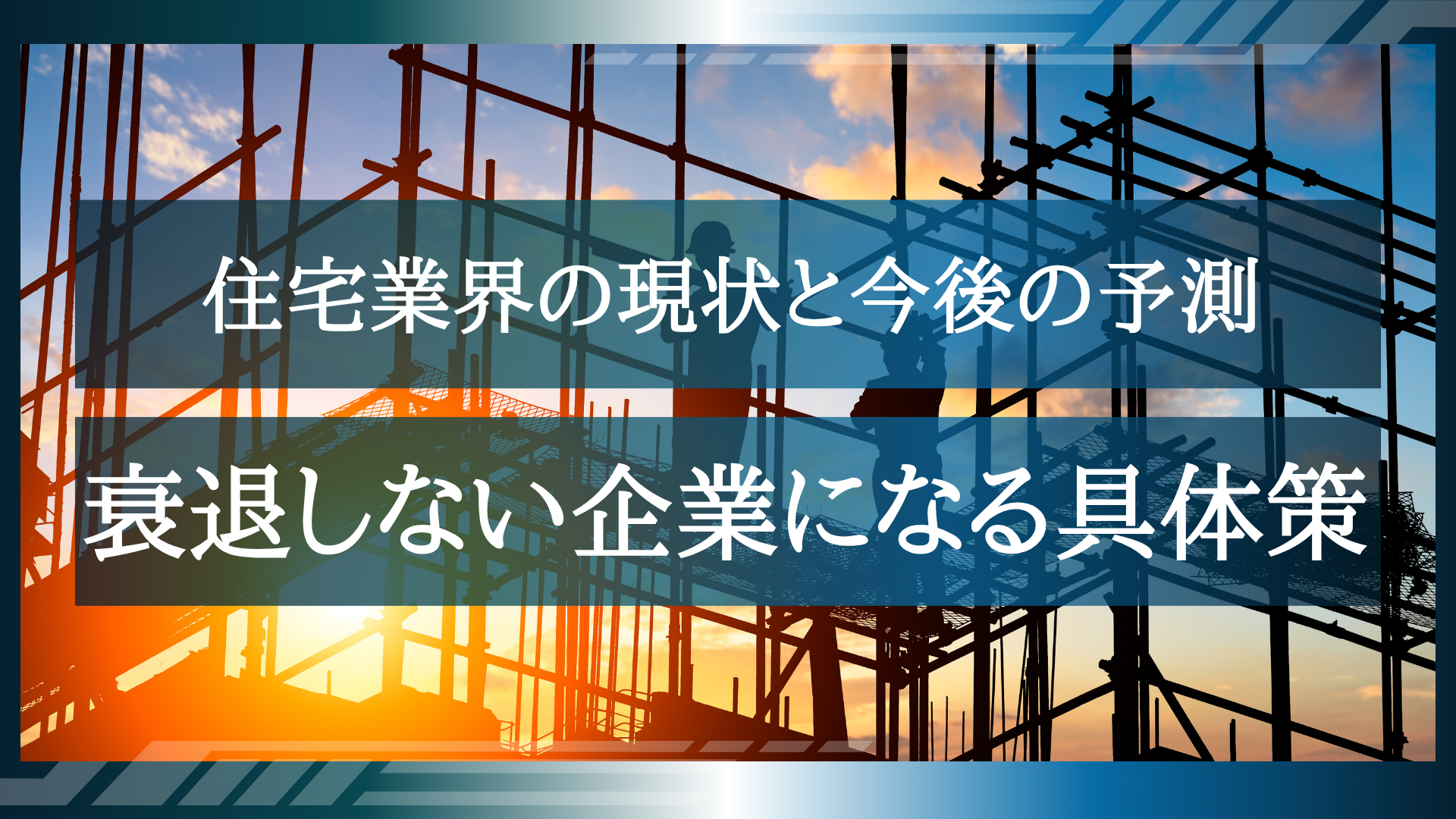
近年、住宅業界では多くの企業が厳しい経営環境のなかで、今後の見通しを慎重に見極めようとしています。
一方で、私たちの生活に欠かせない「衣・食・住」のひとつである「住」を支える、社会的意義の高い魅力的な業界でもあります。
そんな中で、「住宅業界で独立したい」「住宅関連の仕事に就きたい・転職したい」と考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、将来性や安定性について不安を感じている方も少なくありません。
今回は、多くの住宅会社様のWEB集客を支援している当社 が、
住宅業界の現状や今後の動向について、わかりやすく解説いたします。
「住宅業界で自分のキャリアを築いていけるのか」「これからの住宅業界に希望を持てるのか」——
その判断の一助として、ぜひ本記事をお役立てください。
住宅業界の現状
- 住宅業界には多種多様な職種が存在し、設計・施工・販売・管理など、さまざまな専門家が関わり合いながら成り立っています。
その分、社会や経済の動向に左右されやすいという特徴もあります。
特に、近年は以下のような要因が、住宅業界全体の厳しい状況に大きな影響を与えています。
①建築資材や人件費の高騰による 原価率の上昇
②少子高齢化に伴う 人口減少と住宅需要の縮小
③地域によって異なる 住宅建築需要の格差
④現場を支える 職人・労働者の不足と高齢化
これらの課題が複合的に影響し、業界全体としての持続的な成長が求められています。上記③について、ピックアップして見ていきましょう。
住宅建築需要の地域格差
住宅建築の需要は、基本的に人口が多いエリア、特に首都圏を中心に集中する傾向があります。
しかし、例外として「新幹線の延線」や大規模な再開発など、地域特有の要因によって、人口の少ない地域でも一時的に需要が高まるケースも見られます。
一方で、人口減少が進み、特別な需要喚起の要素がない地域では、住宅建築の需要が年々減少しているのが現状です。
そのため、「自社の施工エリア内で住宅建築の需要が減少している」と感じている企業様は、
従来の営業手法に加えて、潜在顧客と出会うための新たな集客戦略を再構築する必要があります。
労働者不足・高齢化
住宅業界は、2011年の東日本大震災以降、
「労働者不足 → 人件費の上昇 → 新築住宅価格の高騰 → 新築需要の減少」
という厳しい循環に直面しています。
もちろん、新築住宅の価格上昇や需要の減少には、労働者不足・高齢化以外にも複合的な要因が関係しています。
さらに、現在の建築業界では「労働者の約43%が50〜54歳」という年齢構成に加え、
DX(デジタルトランスフォーメーション)化の加速により、
10年後・20年後には高度な専門技術の継承が難しくなる可能性も懸念されています。
ここまで、住宅業界が直面している主な課題を整理してきましたが、
このほかにも
・建築基準法における省エネ基準の引き上げ
・住宅ローン金利の先行き不透明感
など、事業環境を左右する要因は多岐にわたります。
次は、今後10年間で住宅業界に訪れる変化の方向性を解説します。
これから住宅業界での企業経営や働き方を検討する方にとっての指針として、ぜひご参考ください。
厳しい現状のまま市場規模が拡大&企業が「衰退」「発展」に二極化
住宅業界は厳しい状況ですが、社会全体の必須産業であることに変わりはありません。
2022年〜2023年に「着工棟数の減少に逆行して工事予定額が増加」という現象が起きていて、住宅業界の現状(原価高騰など)が反映されています。
また「着工棟数が減少している一方で、工事予定額が増加している」という現象から、1棟あたりの建築費が上昇していることが読み取れます。
この傾向を踏まえると、今後10年間の住宅業界の市場規模は、
・着工棟数の観点では縮小傾向
・建築費の観点では緩やかな拡大傾向
を示すと予測されます。
市場規模を支える要因のひとつが、建築費に大きな影響を及ぼす人件費の上昇です。

建築業界全体では、この10年以上にわたり人件費の上昇が続いており、国としても今後、人件費の適正化と賃金改善に取り組む姿勢を示しています。
しかしながら、建築業界全体の労働者数は減少傾向にあります。
そのため、今後の住宅業界における企業の存続と成長を左右するのは、「労働者一人あたりの生産性をいかに高めるか」という点になるでしょう。
住宅業界の事業者が今後10年で「衰退」「発展」に二極化する理由
今後の住宅業界では、「DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進」と「より精度の高い集客戦略の構築」が不可欠な要素となります。

しかし、すべての企業がこれらの変化に柔軟に対応できるわけではありません。
そのため、今後10年間で、変革に対応して成長する企業と、従来の手法に留まり衰退していく企業の二極化が進むことが予測されます。
【DX化が求められる理由】
国は、「良質な住宅ストックの形成」や「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指し、
建築基準法などの関連法令を改正しながら、建築物の省エネ基準を段階的に引き上げる方針を示しています。
これに伴い、住宅設計や書類作成、施工のプロセスがより複雑化しており、
結果として住宅価格のベースが上昇しているというデータも多数報告されています。
こうした変化に対応するためには、業務効率化・設計精度の向上・情報管理の最適化を実現するDXの推進が不可欠といえるでしょう。
住宅業界の中で衰退しない企業になる5つの具体策
これまで、住宅業界を取り巻く厳しい現状や市場規模の動向について整理してきました。
ここからは、こうした変化に対応し、持続的な成長を目指すための具体的な取り組み方針をご紹介します。
住宅業界では、今後次のような方向性が重要になると考えられます。
・省人化(業務効率化や自動化の推進)
・労働者のマルチタスク化(多能工育成による柔軟な現場対応)
・規格化と高付加価値化(標準化による効率化と差別化の両立)
・災害対応・インフラメンテナンス対応(地域貢献型ビジネスの拡大)
・施工エリアや国を超えた事業展開(広域展開・海外進出への対応)
今回は災害対応・インフラメンテナンス対応について、解説します。
災害対応・インフラメンテナンス対応
国および建築業界全体では、今後発生が予想される自然災害や老朽化インフラの問題に備え、
「建築業の専門知識を持つチームの編成」や「自動運転重機の導入準備」など、
災害対応力の強化に向けた取り組みが進められています。
一方で、中小企業様にとっては、発生を正確に予測できない災害への備えを計画的に進めること自体が大きな負担となるケースもあります。
そのため、いざという時に公共工事などの受注に対応できる体制を整えておくことが重要です。
具体的には、次のような取り組みが有効です。
・過去の災害時における建築業者の初期対応・中長期対応の事例を確認し、自社が担える役割を明確にしておく
・過去の災害で国や自治体が実施した支援制度の内容を整理し、活用提案やサポート体制を想定しておく
・自社の財務状況を常に把握し、急な発注増や復旧工事の対応に必要な資金繰りを準備しておく
これらの事前準備を行うことで、災害時における地域貢献と事業継続の両立が可能になります。
厳しい住宅業界の中で効果的な集客戦略
建築住宅業界における効果的な集客戦略は、オフラインとオンラインの手法をバランスよく組み合わせることが重要です。
最適な組み合わせは、企業ごとの事業規模・ターゲット層・地域特性によって異なるため、自社に合った戦略を丁寧に検討する必要があります。

【オフラインでの主な集客方法】
・完成見学会や構造見学会などのイベント開催
・施工エリアを中心としたチラシ・ポスティング
・現場に設置するブランド訴求型の看板 など
【オンラインでの主な集客方法】
・自社WEBサイトの制作・運用によるお問い合わせ導線の最適化
・SNSの活用によるファンづくり・ブランド発信
・リスティング広告やSNS広告などのオンライン広告運用 など
効果的な集客を行うためには、自社の強み・市場環境・予算に応じた戦略を立て、社会情勢やユーザー動向に合わせて柔軟に改善していく姿勢が求められます。
もし、これまで実施してきた集客施策で十分な成果が得られていない場合は、専門のマーケティング会社へ相談することも有効です。
無料相談などを活用し、現状の課題を客観的に分析することで、今後の方向性をより明確にできます。
オンラインを中心とした集客戦略の見直しをご検討中の建築・住宅業者様は、ぜひ プロフィール株式会社へお気軽にご相談ください。
貴社に最適な集客プランをご提案いたします。
まとめ
住宅業界は、人々の暮らしに欠かせない「社会の基盤産業」である一方で、
経済状況や社会情勢の変化に大きく影響を受けやすい業界でもあります。
このような環境の中で、企業が持続的に成長・発展していくためには、
計画的な経営改革と効果的な集客戦略の構築が欠かせません。
本記事でご紹介した内容が、
今後の住宅業界における経営方針の見直しや働き方の検討の一助となれば幸いです。
-------------------------
プロフィール株式会社では、マンパワー不足解消や、集客や追客などをデジタル化し、業務の効率化を目指すご支援をしています。
お困りごともお気軽にご相談ください。
個別相談会は、ZOOMを使用し無料で開催しております。皆様のご連絡をお待ちしております。

