木は、私にとっていつもこの上なく心に迫る説教者だった。
木が民族や家族をなし、森や林をなして生えているとき、私は木を尊敬する。
木が孤立して生えているとき、私はさらに尊敬する。
そのような木は孤独な人間に似ている。何かの弱味のためにひそかに逃げ出した世捨て人にではなく、ベートーヴェンやニーチェのような、偉大な、孤独な人間に似ている。
その梢には世界がざわめき、その根は無限の中に安らっている。しかし木は無限の中に紛れこんでしまうのではなく、その命の全力をもってただひとつのことだけを成就しようとしている。
それは独自の法則、彼らの中に宿っている法則を実現すること、彼ら本来の姿を完成すること、自分みずからを表現することだ。
一本の美しく頑丈な木ほど神聖で、模範的なものはない。
一本の木が鋸で切り倒され、その痛々しい傷を太陽にさらすとき、その墓標である切り株の明るい色の円盤にその木のすべての歴史を読みとることができる。
その年輪と癒着した傷痕に、すべての闘争、すべての苦難、すべての病歴、すべての幸福と反映が忠実にかき込まれている。酷寒の年、豊潤な年、克服された腐蝕、耐え抜いた嵐などが。
そして農家の少年ならだれでも、最も堅く、気品のある木が最も緻密な年輪をもつことを、高い山のたえまない危険の中でこそ、この上なく丈夫で、強く、模範的な幹が育つことを知っている。
木は神聖なものだ。
木と話をし、木に傾聴することのできる人は、真理を体得する。
木は、教訓や処世術を説くのではない。
細かいことにはこだわらず、生きることの根本法則を説く。
ある木が語る。
「私の中には、ひとつの核、ひとつの閃光、ひとつの思想が隠されている。私は永遠の生命の一部だ。永遠の母が私を相手に行った試みと成果は二つとないものだ。私の形姿と私の木目模様は二つとないものだ。私の梢の葉のこの上もなくかすかなたわむれや、私の樹皮のごく小さな傷痕も唯一無二のものだ。私の使命は、この明確な一回かぎりのものの中に永遠なものを形づくり、示すことだ」
ある木は語る。
「私の力は信頼だ。私は自分の父祖のことは何も知らない。私は年毎に私から生まれる幾千もの子どもたちのことも何も知らない。私は自分の種子の秘密を最後まで生きぬく。それ以外のことは何も私の関心事ではない。私は神が私の中に存在することを信じる。私は自分の使命が神聖なものであることを信じる。この信頼に基づいて私は生きている」
私たちが悲しみ、もう生きるに耐えられないとき、一本の木は私たちにこう言うかもしれない。
「落ち着きなさい! 落ち着きなさい!私を見てごらん!生きることは容易でないとか、生きることは難しくないとか、それは子どもの考えだ。おまえの中の神に語らせなさい。そうすればそんな考えは沈黙する。
おまえが不安になるのは、おまえの行く道が母や故郷からおまえを連れ去ると思うからだ。しかし一歩一歩が、一日一日がおまえを新たに母の方へと導いている。故郷はそこや、あそこにあるものではない。故郷はおまえの心の中にある。ほかのどこにもない」
夕方の風にざわめく木の声を聞くと、放浪へのあこがれが私の心を強く引きつける。
私たちが静かに長いこと耳を澄ましていると、この放浪へのあこがれも、その核心と意味をあらわす。それは一見そうみえるような、苦しみから逃げだしたいという願望ではない。それは故郷への、母の記憶への、生の新たな形姿へのあこがれだ。それは家へと通じている。どの道も家郷に通じている。
一歩一歩が誕生であり、一歩一歩が死だ。あらゆる墓は母だ。
私たちが自分の子どもじみた考えのために不安を感じる夕べには、木はそのようにざわめき語る。木は、私たちよりも長い一生をもっているように、長い、息の長い、悠々とした考えをもっている。木は私たちよりも賢い。私たちが木の語ることに耳を傾けないうちは。
しかし木に傾聴することを学べば、そのとき、私たちの見解の短さと速さ、子どもじみた性急さが、無類の喜びを獲得する。
木に傾聴することを学んだ者は、もう木になりたいとは思わない。あるがままの自分自身以外のものになろうとは望まない。あるがままの自分自身、それが故郷だ。そこに幸福がある。
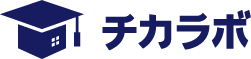

コメントをもっと見るコメントをもっと見る